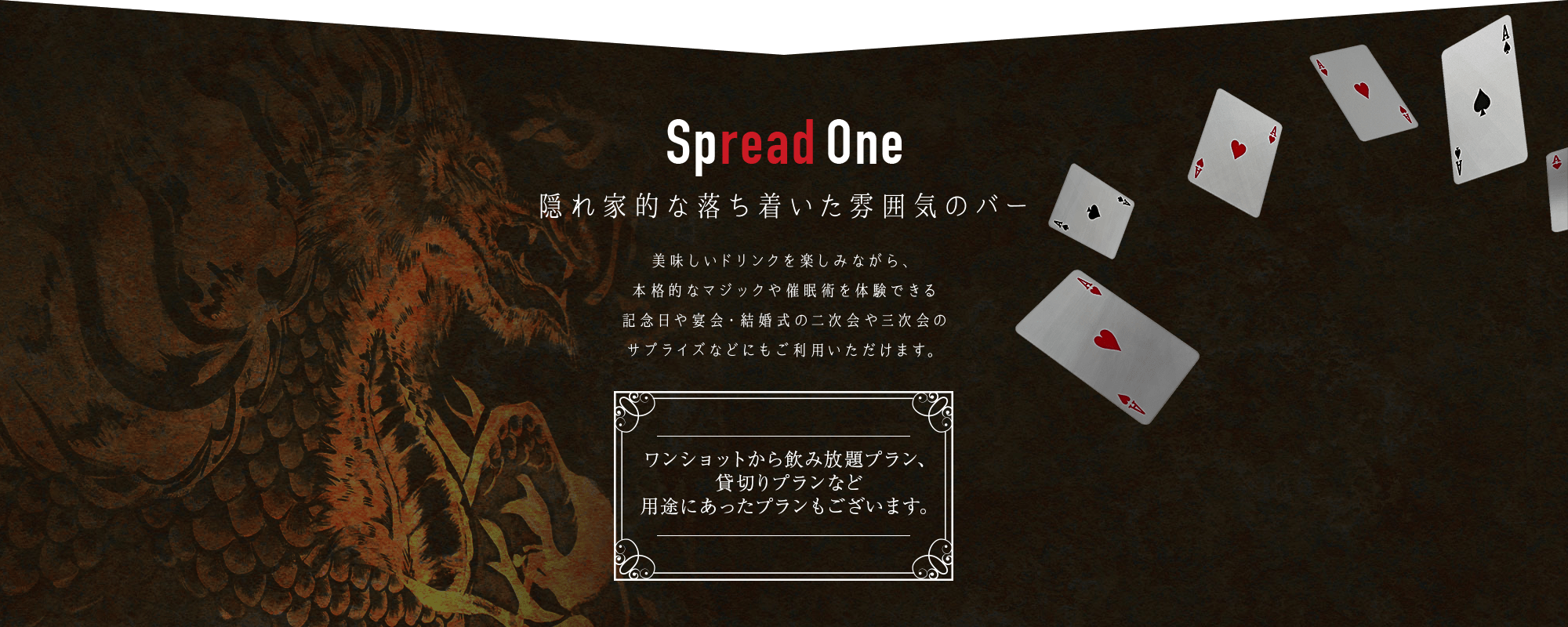古代〜中世――“名のない催眠”が息づいた時代
「催眠術」と聞くと
どこか非日常的で不思議な力を思い浮かべる方も多いかもしれません。
テレビで見るような、手がくっついたり名前を忘れたりする現象。
あるいは、「人を操る」「意識を乗っ取られる」といった
不安なイメージも根強く残っています。
けれど、催眠の本質はまったく異なります。
それは“人を操作する”技術ではなく、“心の奥にある本来の力”を引き出す技法。
そしてその原点は、意外にも日本古来の文化や精神性の中に深く息づいていたのです。
本記事では、催眠という言葉が生まれるはるか以前の日本――
古代から中世にかけて
まだ“名もない意識の技術”として存在していた催眠の原型をたどっていきます。
神官・巫女の「神がかり」――催眠のルーツとしての儀式と信仰

古代日本において、神託や霊的儀式を司ったのは、神官や巫女たちでした。
神楽や祝詞、呪文、舞――それらを通して「神を降ろす」状態に入るという行為は
現代でいう催眠状態と非常に近いものがあります。
繰り返される音やリズム、香り、舞といった五感への刺激は
人の意識を外界から切り離し、内側へと集中させる働きを持っていました。
これは現代の催眠誘導と全く同じ構造です。
「あなたの願いは神に届きました」
「この呪法で病は癒されます」
そうした言葉がもたらす暗示効果は
人の無意識に深く作用し、現実の感覚や感情を変化させていたのです。
陰陽寮と陰陽師――“見えない力”を扱う国家の技法

平安時代、日本には国家機関として
「陰陽寮(おんみょうりょう)」という部署が存在しました。
これは陰陽師たちが所属し、天文・暦・風水・呪術などを司った
いわば“見えない世界”を管理する政府機関です。
陰陽師が行った儀式の多くは、印を結び、呪を唱え
道具を操ることで心身に影響を与えるものでした。
これは現代の催眠でいう“視覚・聴覚・身体感覚”を活用した
多感覚誘導に極めて似ています。
さらに、「方位の制御」や「時間の選定」といった要素は
状況や文脈(フレーミング)を利用して人の心に影響を与える典型例です。
つまり、国家の中枢においてさえ
催眠的な技法が“霊的知識”として制度化されていたことがわかります。
この陰陽寮の存在は
のちに催眠が法的・宗教的に弾圧される時代への伏線とも言えるかもしれません。
修験道・密教・禅――意識を深める“体感の技法”

山伏たちの修行に代表される修験道や、密教の真言行、そして禅宗の坐禅。
これらはすべて、「意識を変容させるプロセス」を含んだ精神修養の技術です。
滝行や断食、読経や念仏――
極限まで集中したり、五感を研ぎ澄ませたりする行為によって
通常の思考を超えたトランス状態へと至る。
これは、催眠における「自己催眠」「深層意識へのアクセス」と同様のプロセスです。
また、禅における公案(こうあん)は
あえて答えのない問いを与えることで思考を停止させ、
直感的な気づきを引き出す手法であり
これも催眠的介入に非常に近い構造を持っています。
名称なき“心の技法”が伝承された理由

このように、古代から中世にかけての日本では、
神職、修験者、陰陽師などが
“無意識に影響を与える技法”を自然に使いこなしていました。
しかし、それらはあくまで宗教的・霊的な儀式の一部として扱われ、
「催眠術」という言葉も概念も存在していませんでした。
それは同時に、現代において「催眠」が持たれるような“怪しい”というイメージが
この時代にはほとんどなかったことも意味しています。
むしろ、「心に影響を与える言葉や所作」は
自然で正当な行為として社会に受け入れられていたのです。
とはいえ、こうした力が“強すぎる影響”を及ぼす危険性を孕んでいることも
古代の人々は直感的に知っていたのかもしれません。
そのため、伝承や儀式は厳格に管理され
一般の人々が安易に扱えないよう制度化されていきました。
後に訪れる“弾圧と名称変更”への伏線
やがて時代が進むにつれ、「人の心を操作する技法」は迷信視されたり
法的に規制される動きが出てきます。
その最初の兆しが、この時代における陰陽寮の形式化や神秘的儀式の管理強化であり
そしてそれは後の明治・大正期における「催眠術禁止令」や「霊術禁止」といった
社会的弾圧へとつながっていきます。
結果として、催眠術師たちは堂々とその名を名乗れなくなり
「気功」「霊気」「霊媒師」など
別の名前を用いて技法を伝えるしかなくなったのです。
しかしその根底には、古代から脈々と続いてきた“名のない催眠”の伝統が
確かに息づいていました。
それは、日本人の精神性に深く根ざした
「静かに内側とつながる力」そのものであったのです。
明治・大正期――西洋催眠の衝撃と日本社会への浸透
文明開化の波が押し寄せた明治時代
日本は急速に西洋の知識や技術を吸収し始めました。
鉄道、郵便制度、洋服、英語、憲法、そして医学や心理学もその対象でした。

この近代化の流れの中で
日本人は「人の心を科学的に扱う技術」としての催眠術と出会うことになります。
それまで“祈り”や“修行”として扱われていた心の働きが
「意識」や「無意識」といった概念とともに、
学術的・理論的に捉え直されていく――。
この時代の催眠術は、日本人の精神文化に大きな衝撃と期待を与えたのです。
西洋から入ってきた「催眠術」という言葉
催眠術という言葉が初めて日本に紹介されたのは
明治初期、ドイツやフランスの精神医学・心理学の文献を通じてでした。
とくにフランスのシャルコーやベルンハイムらの研究が翻訳され
「ヒプノティズム(hypnotism)」という概念が「催眠術」と訳されたのです。

この頃の催眠は
主に「ヒステリー治療」や「記憶の想起」「無意識下の情報へのアクセス」
といった医学的な目的で研究され
日本でも知識人や医師たちが強い関心を寄せていました。
一般市民を魅了したのは「奇跡の芸」としての催眠

ところが、一般市民の間で爆発的な人気を得たのは
学術的な催眠ではありませんでした。
それは、舞台上で披露される“催眠ショー”というエンターテインメントの世界でした。
東京や大阪では、海外から招聘された催眠術師による公演が開かれ、
- 観客が舞台上で眠りに落ちる
- 名前を忘れる
- 自分が猫だと思い込んで鳴き始める
- 急に笑いが止まらなくなる
といった数々の“奇跡”が目の前で展開されました。
人の心と身体が、たった一言で変化する――まるで魔法のような技術に
人々は興奮し、熱狂しました。
この時期には「催眠術入門」や「すぐにかけられる催眠術」
といったタイトルの書籍や冊子が大量に出版され
催眠術は“誰でも使える特別なスキル”として全国に広まっていきます。
「催眠術師になりたい!」――通信講座とブームの拡大
当時の新聞や雑誌には
「わずか数日で習得できる!」
「営業力が3倍になる!」
「相手の心を操る力が手に入る!」
といった広告が並び、
催眠術は一種の自己啓発・実用スキルとしても認知され始めました。
実際に、通信教育や簡易講習会を通じて催眠術を学ぶ人々が急増し
「催眠術師」を名乗る民間人が全国に登場します。
しかし、その急速な広まりと同時に、ある問題が社会に影を落とし始めました。
誤解と混乱、そして“禁止”へ――催眠術の暗い側面
催眠術が広く知られるようになると
次第に「かかりすぎてしまった」「混乱した」「詐欺に使われた」
といったトラブルも報告されるようになります。
その結果、一部の地方自治体では
催眠術に関する営業や公演が禁止・規制される動きも生まれました。
とくに明治末期から大正にかけては、
- 露天や祭りでの「催眠芸」が加熱しすぎたこと
- 心理的ショックを受ける観客の増加
- 催眠を悪用した詐欺事件や医療類似行為の横行
といった背景から
「催眠術=危険」「悪用される技術」という認識が社会に広がっていきました。
その結果、催眠術師たちは表立って活動しにくくなり
「気功術師」
「霊媒」
「霊気使い」
「精神統一師」など
名称を変えて技術を伝承していく流れが生まれます。
この文化は戦後・昭和期にも引き継がれ、現在にまで続いています。
科学と芸のはざまで揺れる催眠術の立場
本来、催眠は人の心にやさしく作用し、癒しや気づきを与える技術であるはずでした。
しかし、社会の理解不足や商業化の波の中で
その本質はしばしば歪められてきたのです。
それでも一部の研究者や医師、教育者たちは催眠の可能性を信じ、
- 精神療法への応用
- 教育現場での集中力開発
- 医療補助技術としての暗示療法
などの分野で、少しずつその価値を見直していきます。

催眠術は、芸術でも魔法でもなく、**「心の言語を話す技術」**である――
その理解は、やがて次の時代である昭和へと、静かに受け継がれていくのです。
昭和――戦争と混乱の時代に見えた催眠術の“二つの顔”
明治・大正の近代化によって日本に広まった催眠術は
「人を操る不思議な芸」としての側面と
「心を整える科学的技術」としての側面を持ちながら
多くの人に知られるようになりました。
しかし、昭和という時代が始まると、社会は激動の渦へと巻き込まれていきます。
昭和初期の不況と軍国主義の台頭、太平洋戦争、終戦、そして混乱と復興――
この長く過酷な時代の中で
催眠術もまた“変化”と“試練”を経験することになったのです。
精神修養と軍事訓練に用いられた“自己暗示”

戦時中の日本では、「強い心」「ぶれない精神」「忠誠心」が何よりも重要視されました。
この風潮の中で注目されたのが
「自己暗示」や「精神統一」といった、内面を強く保つための技法です。
実際、日本国軍内には
催眠術や精神制御を専門とする非公式の研究機関が存在していた
という説も残されており
一部の兵士や特殊任務部隊に対して
集中力や精神安定のための催眠的訓練が行われていたと言われています。
軍事訓練の中には
瞑想や黙想、呼吸法、反復的な言葉の唱和などを取り入れたものも多く
兵士たちに「自分は恐れない」「任務を完遂する」
といった信念を植え付けるための訓練が行われていました。
これらはまさに、催眠的な技法であり
暗示の力を応用した「意識と無意識の訓練」だったのです。
ただし、それが「国家のため」「命令に従うため」に使われたことで、
催眠の持つやさしさや癒しとはかけ離れた
“従属のツール”としての顔を持つようになってしまいました。
“禁止された技術”として地下に潜った催眠術
戦中・戦後の混乱期、日本国内では再び催眠術に対する規制と偏見が強まり、
公的な場で催眠を名乗って活動することが難しくなっていきます。
この時代、多くの催眠術師たちは表向きに
「気功師」
「霊術家」
「精神鍛錬指導者」などと名乗り
その技法を別の形で伝えていました。
彼らの中には、かつて西洋催眠を学んだ者や軍事訓練に携わった者もおり、
戦後の混乱を乗り越えて、“心の回復”の技術として静かに催眠を残していったのです。
こうした「名称を変えた催眠技術」は
のちの昭和後半〜平成時代のスピリチュアルブームとも結びつき
形を変えて現代へと受け継がれていくことになります。
娯楽と再生の中で“再発見”された催眠術
終戦後、日本は焼け野原からの復興をめざし、急速な経済成長とともに、
生活や文化にも「楽しみ」や「癒し」を取り戻していきます。

昭和30年代から40年代にかけて
テレビという新しいメディアが家庭に普及しはじめると
催眠術は再び「不思議な芸」として、人々の前に姿を現すようになります。
テレビ番組では、催眠術師が一般の人を眠らせたり
記憶を変えたり、性格を一時的に変化させたりする様子が放送され
視聴者はその様子に驚き、笑い、目を見張りました。
このとき、日本人の多くが
「催眠術=テレビで見る不思議な現象」として強く印象づけられたのです。
一方で、そこに登場する催眠術師たちは、相手を支配するのではなく、
安心感を与え、笑顔を引き出すことを重視しており、
催眠の持つ“やさしさ”と“楽しさ”が再び社会に受け入れられるようになっていきました。
催眠が芸として受け入れられた理由
この時代の日本人は、戦争によって
「本音を言えない社会」「感情を抑える習慣」の中に生きていました。
その中で催眠術によって突然笑い出す、泣き出す、踊り出す――
そんな素直な反応を目の当たりにした視聴者は
まるで“自分の心の奥”を見ているかのような共鳴を感じたのです。
つまり催眠術とは、「人が無意識に抱えているものを解放する芸」であり、
それは当時の日本人にとって、癒しであり、希望でもありました。
また、子ども向け番組やバラエティでもたびたび催眠術が登場し、
「催眠って面白い」「不思議だけど怖くない」と感じる世代が増えていったことは、
のちの平成・令和時代に向けた催眠術の地盤づくりとなっていきます。
心を扱う技術としての再評価

昭和の後半に入ると、心理学や自己啓発といった分野が一般にも広まり、
「人の心にアプローチする技術」に対する関心が高まっていきます。
催眠術も、「ただの芸」ではなく「潜在意識に働きかける実用的な方法」として
一部の教育者やセラピスト、研究者の間で見直され始めました。
被暗示性の研究と誤解
昭和期のテレビ番組では
催眠にかかる人とかからない人が混在する場面が多く見られました。
このことから
「催眠術は特別な人にしかかからない」
「自分には無理」
といった誤解が広がっていきました。
一方で、学術的には「被暗示性(ひあんじせい)」という概念が注目され、
暗示に対する反応のしやすさには個人差があること、
そしてその差は先天的ではなく、信頼関係や心理的安全性
集中力やイメージ力によって変化することが明らかになっていきました。

つまり、誰にでも“催眠に入る可能性”はあり
適切な誘導と環境が整えば、
それは「特殊な能力」ではなく
「心の自然な反応」として起こるという理解が広まっていきます。
昭和という時代が残した“催眠の遺産”
戦争の傷を抱えながらも、日本は高度経済成長を遂げ
心の自由や表現が広がっていった昭和。
その中で催眠術は、時に名前を変えながらも
変わらず“心の可能性”と向き合い続けてきました。
娯楽の中に潜む癒し。
スピリチュアルと結びついた深層意識。
教育や医療、スポーツへの応用。
そして、無意識との対話という“見えない力”の尊重――
それらすべてが、現代へと続く催眠術の「二つの顔」を形づくっていったのです。
平成・令和――催眠が“癒しと成長”の技術として見直された時代
昭和の終わりから平成へと時代が変わると、日本社会は目まぐるしく変化していきます。
バブル崩壊、終身雇用制度の崩壊、情報化社会の加速、SNSの普及。
人々の心は「モノの豊かさ」から「心の安らぎ」へと関心を移していきました。
この時代の変化の中で、催眠術は“エンタメ”の枠を超えて、
癒し・自己成長・スピリチュアルな探求の手段として、再び注目されるようになります。
特に、戦後に一度失われかけた「催眠術」の名称そのものが、
平成以降のセラピー・教育・精神性の分野でゆっくりと復権していくのです。
ヒプノセラピーという新たな形

平成初期、日本では「催眠療法(ヒプノセラピー)」という言葉が
少しずつ知られるようになりました。
これは、催眠状態を使って無意識とつながり
悩みやトラウマ、思い込みの根本にアプローチするセラピーです。
欧米では既に広く実践されていたこの技法が、日本にも輸入され、
- 前世療法
- インナーチャイルドセラピー
- 潜在意識の書き換え
- トラウマ解放
といった多彩な手法が一般に普及していきます。
この中には、戦中・戦後の「催眠術」が名称を変えて継承されてきた
“霊気”“気功”“精神統一法”などと融合したケースも多く
かつて弾圧された技術が、より柔らかな形で社会に還元されていく過程でもありました。
「心を整える」ブームと自己変容への関心
平成後期から令和にかけて
日本では“マインドフルネス”や“自己啓発”といったキーワードが広く浸透していきます。
ビジネス書やYouTube、SNSを通じて
「瞑想」
「潜在意識」
「思考の書き換え」
といったテーマが注目を集め、
人々の関心は「成功するための努力」から
「整った自分で生きる」という在り方へと移っていきました。
その流れの中で
「催眠を学びたい」「自分の潜在意識に触れてみたい」と願う人が急増し
一般向けの催眠講座やヒプノセラピー体験会が各地で開催されるようになります。
かつては“特別な力”として誤解された催眠術が、
いまでは「心の使い方」として、多くの人の手に戻ってきているのです。
スピリチュアルとの融合と“魂の癒し”としての催眠
平成後半から令和にかけて
ヒプノセラピーはスピリチュアルな分野と深く結びついていきます。
とくに注目されたのは
「前世療法」や「魂の記憶」にアクセスするというアプローチ。
アメリカの精神科医ブライアン・L・ワイス博士の著書などの影響もあり、
日本でも「前世からの課題を知る」「魂の旅を思い出す」といった目的で
催眠を受ける人が増加しました。
また、「ハイヤーセルフとの対話」や「守護霊からのメッセージを受け取る」
といったテーマも扱われるようになり
催眠は“目に見えない世界”とつながるための方法としても
支持されるようになります。
ここには、かつて法的に名称を変えざるを得なかった催眠術師たちの知恵――
「気功」「霊気」「霊媒」といった
“スピリチュアルの名を借りた催眠技術”が、
新しい形で融合・再評価された側面もあるのです。
セルフ催眠とSNS時代の自己ケア

令和時代に入り、YouTubeやTikTok、InstagramといったSNSの普及によって、
催眠や潜在意識に関する情報が誰でもアクセスできるようになりました。
- 「自分でできるセルフ催眠」
- 「3分で潜在意識にアクセスする方法」
- 「寝る前に聴くだけで人生が変わる催眠音声」
といったコンテンツが日常的に目に入るようになり、
かつては閉ざされた技術だった催眠が
“日常生活の中で使えるツール”として急速に広まっていきます。
今では、スマホ1台で催眠誘導を体験できる時代。
それはつまり
「誰もが自分の無意識とつながれる時代」に入ったということでもあります。
ビジネス・教育・スポーツへの応用

催眠の再評価は、スピリチュアルやセラピーの枠にとどまりませんでした。
令和に入り、ビジネスや教育
スポーツといった“現実の成果”が求められる場面でも
催眠的アプローチが重要視されるようになります。
たとえば、
- プレゼンや試験前の緊張緩和
- 習慣の書き換え(禁煙・ダイエット・睡眠)
- スポーツ選手のイメージトレーニング
- 子どもの自己肯定感を育てる言葉がけ
など、催眠の本質である
「暗示」「イメージ」「無意識の活用」が、あらゆる分野で実践されています。
これらは、かつて“怪しい”とされ弾圧された催眠術の技法が、
科学的根拠と実績をもって、社会に受け入れられた証でもあります。
多様性の時代にマッチした“個人最適化の技術”
令和の社会は、「正解が一つではない時代」とも言われます。
性別、職業、生き方、価値観――人それぞれの在り方が認められつつある中で、
「自分に合った心の扱い方」が求められるようになってきました。
催眠はまさに、その“個人に最適化されたアプローチ”を可能にする技術です。
- 誰かの成功法則をなぞるのではなく、自分の内側から納得を得る
- 他人に励まされるのではなく、自分の無意識から勇気をもらう
- 訓練ではなく、感覚とイメージによって自然に変化していく
これらは、催眠的アプローチの中核にある“やさしく、深く働きかける技術”です。
旧来の「強制的にがんばる」方法ではなく、「内側から力を引き出す」方法――
それこそが、今の時代に合った成長のかたちではないでしょうか。
教育・子育ての中に息づく暗示の力
現代の教育や子育ての中でも、催眠的要素が静かに根を広げています。
たとえば、「褒めて伸ばす」「否定せずに聴く」「安心感を与える」という育児法は、
無意識に働きかける“前向きな暗示”の一例です。
また、幼児期・思春期は暗示に対する感受性が高い時期でもあり、
このタイミングでどんな言葉をかけられたかが、
その子の自己像や人生観に強い影響を与えます。
催眠という言葉は使われていなくても、
“ことばが心を形づくる”という催眠の本質は
今も教育現場で静かに息づいているのです。
「かけられる」から「使いこなす」へ――意識の変化
かつて催眠術は、「人にかけられる特別な技術」として知られていました。
テレビや舞台での催眠ショーの影響もあり、
「催眠=他人に操られるもの」「かかるかどうかは才能次第」
という誤解が根強く残っていました。
しかし、令和の今
催眠は「誰でも学べる」「自分で使いこなせる」技術へと進化しています。
- モチベーションを高めたいときに自己暗示を使う
- 習慣を変えたいときにイメージを活用する
- 自分らしさを取り戻したいときに深呼吸と内省で無意識に触れる
こうした日常的な行動の中に、催眠のエッセンスはたくさん含まれているのです。
今では講座やセッションを受けるだけでなく、
自分自身が“催眠を通して人生を整える”時代が到来しているのです。
催眠の魅力は「目には見えないけれど確実に感じられる変化」

催眠を体験した多くの人が
「何かが変わった気がする」「前より心が軽くなった」と語ります。
それは、無意識という深層にやさしく触れ
そこに新しい視点や感覚を送り込むからです。
私たちの行動や感情の多くは
思考よりも先に“無意識”によって決められているとも言われます。
だからこそ、言葉では説明できない
「なんとなくの不安」や「やる気が出ない理由」も
催眠を通して初めて明らかになることがあるのです。
一度、心の奥に静かに耳を傾けてみる――
それだけで、人生が少しずつ変わり始めることがあります。
そして、これは特別な能力ではありません。
誰の中にもある“内なる感性”に働きかける、やさしくて静かな技術。
それが、催眠という方法なのです。
催眠の時代は“これから”かもしれない
ここまで、日本における催眠術の長い歴史を振り返ってきました。
時に禁止され、名称を変え、見えない場所で受け継がれてきたこの技術は
いまようやく「本来の価値」を取り戻しつつあります。
「人を操る力」ではなく、
「自分を整え、癒し、導く力」として――。
科学的な裏付けと、精神的な深みが融合する時代において、
催眠術は再び、人々の生き方や可能性に寄り添う存在となっているのです。
そしてあなたへ――本来の自分に還る旅の入口
催眠とは、誰かにかけられる魔法ではありません。
それは、あなた自身の心にある“静かで力強い場所”に戻る方法です。
悩みを解決するためでも、やる気を高めるためでも、
もっと自由に、もっと自分らしく生きたいと思ったとき――
催眠という心の技術が、きっとあなたを優しく導いてくれるはずです。
心の旅を、今ここから――Spread Oneで体験できること

催眠は特別な人のための技術ではなく、
どんな人にも、自分の心と向き合う力を取り戻すきっかけになります。
けれど、自分ひとりで“内側の旅”を始めるのは
少し不安に感じることもあるかもしれません。
だからこそ、安心できる空間と信頼できるガイドの存在が、とても大切です。
Spread Oneでは、
あなたの中にある無意識の可能性を
やさしく、丁寧に引き出すセッションをご提供しています。
- 潜在意識を書き換える体験
- 自己催眠や暗示の実践法
- ヒプノセラピー・気功・メンタルトレーニングを統合した独自メソッド
それらはすべて、あなたが「本来の自分に還る」ための道具です。
今この瞬間も、あなたの中には無限の力が眠っています。
もしその扉を開けてみたくなったら――
どうぞお気軽に体験セッションへお越しください。
あなたの心の旅が、ここから始まることを願っています。
▶ 詳細・ご予約
お問い合わせはこちらから