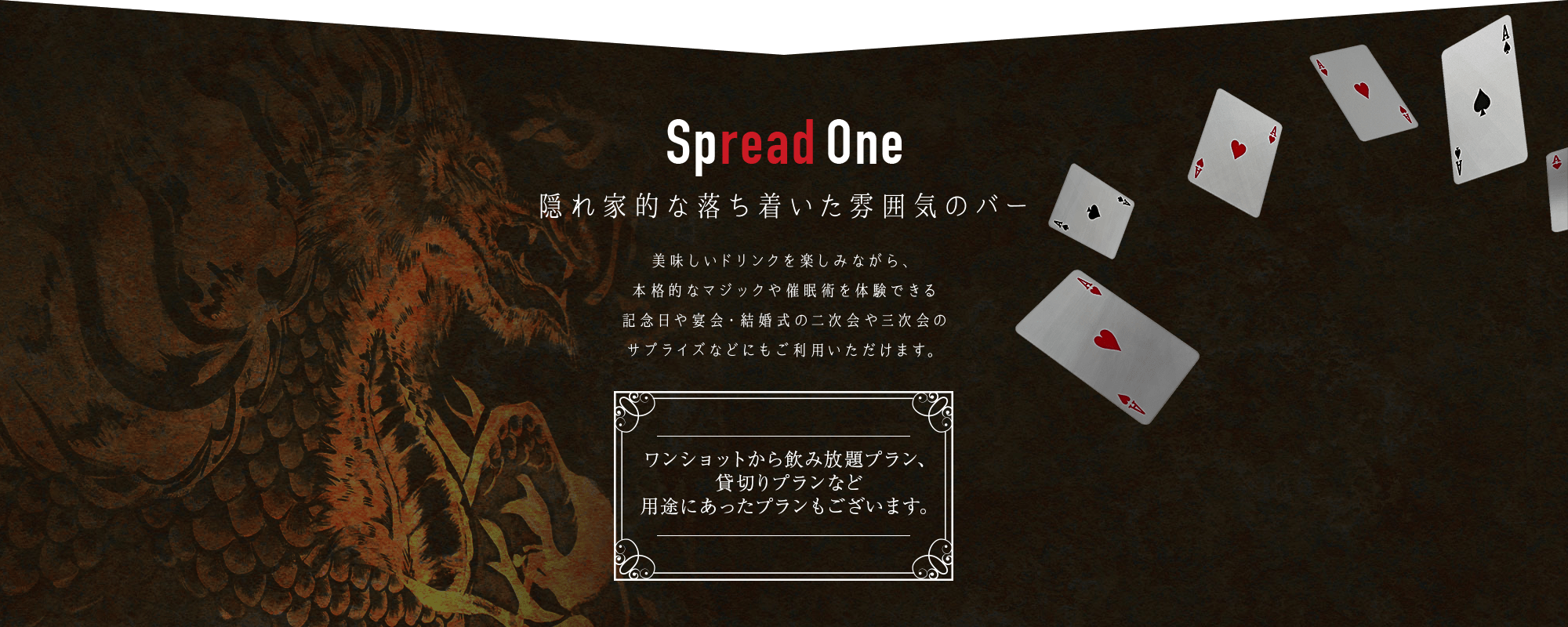“見えないもの”は本当にいないのか?――幽霊を信じる心のしくみ

たとえば夜道を一人で歩いていて、ふと背中に何かの気配を感じることがあります。
振り返っても誰もいない。
けれど、そこに“何か”がいた気がして、心臓が早くなり、呼吸が浅くなる。
まるで自分の体が、「ここには何かいる」と訴えているように。
この瞬間、実際に誰かがいたかどうかは問題ではありません。
あなたが感じた“気配”は、紛れもなくあなたの現実の一部として存在していたのです。
「幽霊はいるのか?」という問いは、昔から人々の心を惹きつけてやみません。
それは単なるホラーの話題ではなく、
「私たちは何を“存在”と感じているのか?」という、
もっと深い問いを内包しています。
この世界には、目に見えるものと、
見えないけれど感じられるものがあります。
私たちが「存在する」と信じているものは、すべて五感で確認できるものでしょうか?
あるいは、心の中で“確かにある”と感じたとき、
それもまた存在すると言えるのでしょうか。
子どもがぬいぐるみに話しかけるとき、
そのぬいぐるみはただの綿と布ではありません。
そこに命が宿っているかのように話しかけ、笑いかけ、時には涙を流す。
大人から見れば「空想」に見えるかもしれませんが、
子どもの世界では、それは確かな現実なのです。
同じように、私たち大人も、誰かの思い出を胸に生きたり、
音楽や本に心を揺さぶられたりします。
そうした“形のない体験”が、日々の気持ちを大きく左右することもあるでしょう。
こうした体験が積み重なったとき、ある種の「存在感」が生まれます。
それは物としてそこにあるわけではないけれど、
“感じられる存在”として、私たちの心に影を落とします。
幽霊という存在は、そうした“感じられる現実”の象徴でもあるのです。

では、この“感じられる現実”とはいったい何なのでしょうか?
たとえば図書館の本を想像してください。
棚に並ぶ本は、どれも紙とインクでできた物質です。
しかし、その中に込められた物語、登場人物の感情や運命、
読み手の記憶や共感――それらはすべて形を持ちません。
けれど、読んだ人の中では“確かに起きた出来事”として残っていきます。
また、スマートフォンの中にある写真やメッセージもそうです。
ただのデータにすぎないのに、
そこには懐かしい思い出や、愛情、悲しみ、感謝が詰まっています。
指先で触れられないその感情の数々は、まぎれもなく“現実”の一部なのです。
ここで少し脳の働きに目を向けてみましょう。
近年の脳科学では、
「私たちが見ている現実は、脳が予測して構築しているものである」
という考え方が主流になってきています。
これを“予測処理モデル”といいます。
私たちの脳は、外から入ってくる情報をただ受け取っているだけでなく、
「きっとこうなるはずだ」という予測を常に行い、それを現実として体験しています。
たとえば、暗い廊下を歩いているとき、
急に物音がすると心臓が跳ね上がるのは、脳が「もしかして誰かがいる?」と予測し、
体を“準備モード”に入れるからです。
つまり、「誰かがいる」という感覚は、実際の存在よりも、
脳が先回りして作ったイメージによって生まれるのです。
このように、現実は“感じる側”によって変わるというのが、
今の脳科学のスタンスです。

そして、これをより強く裏付ける有名な実験があります。
1970年代、カナダで行われた
“フィリップ実験”と呼ばれるプロジェクトをご存知でしょうか。
これはある心霊研究チームが、
「幽霊は人間の想像力によって作れるのか?」を検証するために行ったものです。
研究者たちは、実在しない人物“フィリップ”のプロフィールを創作しました。
17世紀の貴族で、愛人をかばって自殺したという悲劇的な物語を設定し、
肖像画まで描いて徹底的にリアリティを持たせました。
参加者たちはそのフィリップを本物と信じて、定期的に降霊会を開きました。
すると、何も起こらなかったはずの会場で、
ノック音や風、テーブルの揺れといった現象が起こり始めたのです。
さらには、「1回ノックで“はい”、2回で“いいえ”」というルールまで成立し、
幽霊とのコミュニケーションが“できる”ようになったと記録されています。
これはもちろん、幽霊そのものの実在を証明するものではありません。
しかし、ここで重要なのは、**「信じたものが現実に影響を与える」**という点です。
誰もいないはずの場所に、“いる”という前提で人が集まり、
感情を込めて向き合い続けると、
その空間には確かに“何かが存在している”ような体験が生まれるのです。
幽霊とは、こうした「心が作り出したリアリティ」の集積かもしれません。
物理的に誰もいなくても、「ここには何かがいる気がする」という感覚は、
決して錯覚や妄想とは言い切れないのです。

他にも、1992年のイギリス。
BBCが放送した一本のテレビ番組が、国中を恐怖に陥れました。
番組の名前は『Ghostwatch(ゴーストウォッチ)』。
それは一見すると「心霊現象を生中継で検証する」という趣旨の
ドキュメンタリーでした。
ロンドン郊外の住宅で、少女が見えない存在に悩まされているという設定。
スタジオのキャスターと現場のリポーターが、
視聴者と一緒に“怪奇現象”を目撃していく構成。
しかしそれは――すべて事前に用意されたフィクションだったのです。
ところが、番組が進行するうちに、
まるで何かが本当に“入り込んできた”かのような演出が始まりました。
突然のノイズ、カメラの不具合、画面にちらりと映る謎の人影。
現場が混乱し、スタジオも異常事態に。
視聴者は何が現実で何が演出か分からないまま、不気味な終幕を迎えます。
事前に「これはフィクションです」と告知されていたにもかかわらず、
放送後、BBCには数万件の電話が殺到。
「子どもが夜眠れない」「家に幽霊が来た気がする」「パニックになった」――
中には心的外傷に近い症状を訴えた家庭もあったといいます。
つまり、“存在しないはずの幽霊”が、
テレビを通して、多くの家庭に“入り込んだ”のです。
ここで思い出してほしいのが、前半で紹介したフィリップ実験です。
創作された人物が“いるかのように振る舞いはじめた”あの現象。
そしてGhostwatch事件では、フィクションであることを知っていた人たちすら、
本気で恐れを抱き、記憶の中では「本物だった」と語ってしまう。
このふたつに共通するのは、
“そこにいないもの”が“確かにいた”という感覚のリアリティです。

では、私たちの脳や心は、
どうしてこのような“見えないはずのもの”を“感じてしまう”のでしょうか?
答えは、「人間の脳は、意味を見つけようとする装置だから」です。
私たちは暗闇の中で物音がすれば、“風”ではなく“誰か”の気配を想像します。
鏡に映った一瞬の影を、実際の動きより“幽霊かも”と解釈してしまいます。
これはただの錯覚ではありません。
私たちは、常に“意味”を探して生きているのです。
この“意味を探す力”は、本来とても大切な能力です。
大切な人の言葉の裏にある想いを読み取る。
空気を察して行動する。
芸術に心を動かされる。
いずれも、「目に見えないものを感じ取る」力です。
そしてその力が、幽霊という存在に命を与えるのです。
たとえば、家族や友人を亡くしたあと、その人の気配を感じることがあります。
誰もいない部屋に入った瞬間に、ふと懐かしい香りが漂ったり、
思い出の曲が耳に届いたりする。
それは幻でしょうか?
いいえ、そこに“意味”があると感じたなら、それはもうあなたの世界の一部です。

科学的には、それは「記憶が作り出す体験」だと説明されるかもしれません。
でも、体験している本人にとっては、まぎれもない“リアル”なのです。
「でもそれって、実在とは言えないんじゃない?」
そう感じる方もいるでしょう。
たしかに、計測できないもの、証明できないものを“存在する”と言うのは、
科学的には慎重であるべきです。
けれど一方で、私たちは毎日、計測も証明もできないものに囲まれて生きています。
たとえば“愛”や“希望”や“夢”。
それらを誰も「見たことがない」のに、「ある」と信じて疑いません。
なぜでしょう?
それは、それらが“私たちに影響を与えるから”です。
幽霊も、同じかもしれません。
実体はなくても、そこに“意味”が生まれ、
人が反応し、語り継がれ、場所に記憶が刻まれていく。
それは、ひとつの「存在のかたち」なのではないでしょうか。
少し話が変わりますが、“場の空気”という言葉があります。
誰も喋っていないのに
「今日はちょっと重いな」「なんか変な感じがする」と感じることがあります。
それは空気の化学成分でも、温度でもありません。
でも、確かに“何か”を私たちは感じ取っています。

このように、“形のない何か”が、
私たちの感情や行動に影響を与えている場面は、日常にいくらでもあります。
つまり、“いないもの”を“いる”と感じる力は、
私たちの中に最初から備わっているのです。
その力が時に過剰に働けば、“幽霊”を見てしまうかもしれない。
でも、それはただの錯覚でも妄想でもなく、
「感じるという能力が正しく作動した結果」かもしれません。
ここで、最初の問いに戻りましょう。
――幽霊は、いるのか? いないのか?
答えはとてもシンプルで、そして少し詩的です。
「あなたが“いる”と感じたなら、そこには“いる”」
それは物理的な存在ではないかもしれない。
けれど、感情として、記憶として、恐怖や愛着として、
その存在は確かにあなたの世界に現れています。
そして、あなたがそう感じたということが、何よりの“証拠”なのかもしれません。
幽霊とは、単なる霊的存在ではなく、
私たちの“感じる力”が作り出した、もうひとつの“現実”なのです。
もし、ここまで読んでくださったあなたの中に、
「やっぱり、目に見えない何かってあるのかもしれない」
そんな気持ちが少しでも芽生えていたら――
その“なにか”の正体について、
もう少し深く、柔らかく、でも真剣に語り合ってみませんか?
松山のCafe & Bar「Spread One」では、
目の前に見える現実と、心の奥にふと立ち上がる気配とのあいだを、
科学や心理、直感や哲学、スピリチュアルな感性――
さまざまな角度からやさしく紐解くような夜を過ごすことができます。
たとえば、
・脳がどのように“現実”を感じているのかという最新の神経科学の話
・感情がどんなふうに記憶を形づくるのかという心理学の視点
・人の思念が空間に影響を与えるという、場の“波”に関する感覚的な体験
・世界各地の文化や伝承に宿る、見えないものへの敬意のあり方
・そして「信じる」ということが、どれほど深く私たちを動かしているのかという問い
それらを、ただの知識としてではなく、
あなたの感覚と、あなた自身の言葉で向き合えるような空間があります。
ここでは、答えを決めつけることはありません。
“見えること”と“感じること”、
“説明できること”と“ただ確かにあるもの”、
その境界をふわりと撫でながら、
自分なりの世界の捉え方を見つけるお手伝いをしています。
ひとりでふらっと来ても、誰かと語り合っても構いません。
なにかを証明する場所ではなく、なにかを“感じ直す”場所。
それがSpread Oneです。

もし、あなたの中にまだ言葉になっていない「なぜか気になるあの感覚」があるなら、
その続きを、ここで一緒に見つけてみませんか?
見える世界と、もうひとつの世界のあいだで。
あなたの感性が目を覚ますのを、そっとお待ちしています。
お店では、こう言ったお話を
さらに深堀して、なぜなのか?を説明したりしています。